NICE PEOPLE


海と未来をつなぐ「team長崎シー・クリーン」の挑戦
野母崎で活動する「team長崎シー・クリーン」。発起人であるデミー博士をはじめ、学校関係者や漁師・主婦・学生などが集い、現在18名で活動しています。「軍艦島が映える海を守ろう」という想いが、このチームを動かしています。


team長崎シー・クリーンの皆さん
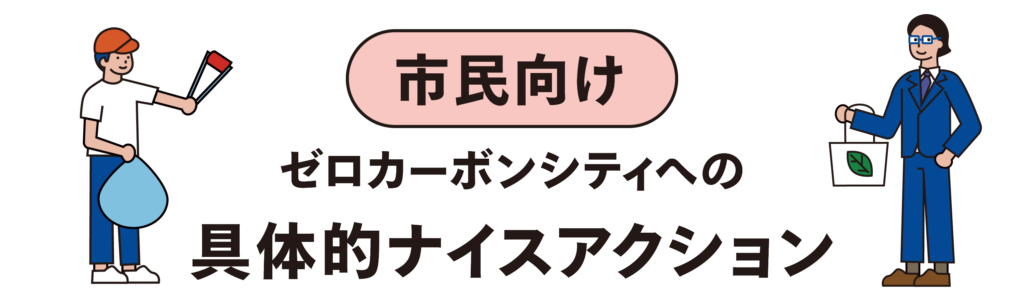


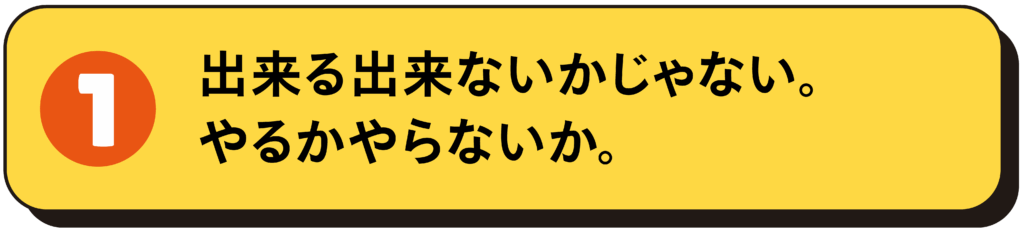
team長崎シー・クリーンとは?
―「team長崎シー・クリーン」の活動内容を教えてください。
デミー博士:
「軍艦島が映える海を守ろう」を掲げ、軍艦島が見える海岸や道路・港の美化活動に取り組んでいます。他にも、環境教育、生態系の保護、地域の魅力発信、アート活動など様々な活動をしています。
team長崎シー・クリーンの主な活動
(1)海岸、河川、港、道やその周辺の清掃・美化
(2)環境教育、環境調査・研究
(3)海洋生物多様性の保全・保護
(4)地域資源の活用、地域振興、地域活性化
(5)地域の魅力発信
―どのようなメンバーがいるのですか?
デミー博士:
現在、会員は18名。主に野母崎の方々と市内の方々です。メンバーには、学校の先生や漁師さん、市役所・県庁の方、主婦、高校生や中学生と、いろんなかたがいるんですよ。
少人数で始めた活動ですが、熱い想いを持っている方・協力してくれそうな方に話をして、仲間を増やしてきました。そうするうちにキーマンが集まってきた感じですね。

―結成のきっかけは何だったのでしょうか?
デミー博士:
コロナ禍で観光客や釣り客が増えたことにより、野母崎地域ではごみの問題が目立つようになりました。そこで、まずは道路のごみ拾いを始めました。
また、戸石漁港でカキ焼きを楽しむ際には、「その前にまずごみを拾ってから食べよう」と呼びかけるなど、小さな取り組みを続けていました。
そんな活動を何年か続けるうちに「どうせやるなら、もっと本格的に取り組もう」と思うようになり、2021年4月に「team長崎シー・クリーン」を立ち上げました。
―どのような方がごみ拾いに参加しているのでしょうか?
デミー博士:
「ごみ拾いをしたいけど、なかなかきっかけがない」「子どもと一緒に参加したいけど、機会が少ない」──そんな方たちが、よく参加してくださいます。最近では子ども会などの地域の集まりも少なくなってきているので、そうした活動の場が求められていると感じます。
先日は、新入生の歓迎遠足前に「ビーチクリーン大作戦」を実施しました。「きれいな海で迎えよう」と呼びかけたところ、多くの方が参加してくれました。やはり参加のきっかけづくりが大事だなと感じています。

―参加者は地元の人が多いのですか?
デミー博士:
地元の方が多いですが、県外から参加される方もいますよ。
テレビ・新聞で取り上げられているのを見て来てくれてるのと、僕の講演で興味を持った方が来てくれます。
他にもホームページやSNSで発信しているので、飛び込みでいらっしゃる方もいます。
―ロータリークラブ・商工会で講演したりもされていますが、特に重点的に伝えていることはありますか?
デミー博士:
まずは、子どもたちの頑張る姿を見てもらうようにしています。発表やプレゼンの映像、ニュースで取り上げられた場面など、子どもたちが自分の言葉で思いを伝える姿は心に響くんですよね。
そうした映像をきっかけに、「自分も何かやってみようかな」と思う方が増えていると感じます。

―子ども達・若い世代の環境意識について、どのように感じていますか?
デミー博士:
意識が高い若者が多いのかなと思うことはあります。僕たちは普段、環境意識の高い人たちと関わるので、特にそう感じるのかもしれません。
環境という視点だけではなく、子どもたちにはぜひ地域とつながる活動に参加してほしいと思っています。地域を知ることで愛着が生まれ、将来もその地域に残ったり、戻ってきたりするきっかけになりますから。
―発信の仕方も工夫されているとか。
デミー博士:
はい。ウェブサイトやSNSを活用し「戦略的な情報発信」に力を入れています。自分たちで発信するだけでなく、メディアに取り上げてもらうことで、より多くの人に届けられるよう意識しています。
他にも地域の学校とも連携して授業で取り上げてもらったり、ビラを配ったりしながら、幅広く周知を図っています。

廃棄野菜でウニ養殖!
―今日は「ウニ養殖」の様子を見せていただけるとのことですが、そもそもこの取り組みはどんな背景から始まったんですか?
デミー博士:
今、海の中では「磯焼け」が進んでいて、海藻がどんどん減ってきているんです。海藻がなくなると魚が卵を産む場所も減りますし、ウニにも身が入らなくなってしまう。なのにウニは繁殖力が強くて、数は増え続けていて、海の中が“ウニだらけ”になっている場所もあるんですよ。
―ウニだらけ!
デミー博士:
野母崎三和漁業協同組合の漁師さんたちは、身の入らないウニを定期的に潜って駆除しています。そのウニはこれまで捨てられていたので「何か活かせないか」と考えました。
県内では見た目などの理由で出荷できない廃棄野菜がたくさんあります。JA全農ながさきさんから廃棄野菜を提供してもらい、駆除したウニのエサにしています。捨てられていたウニと野菜を組み合わせて美味しいウニを育てる、という挑戦です。
team長崎シー・クリーンと野母崎三和漁業協同組合、JA全農ながさきさ、3団体のコラボプロジェクトですね。

―いつから取り組まれているのですか?
デミー博士:
昨年の11月からスタートして、今5カ月ぐらいです。今日で1クール目が終わり、次から第2クールに移行します。
今日は、育てたウニをみなさんに試食してもらう日なんです。お披露目会というほどではありませんが、この活動を少しでも多くの方に知っていただけたらと思っています。
メンバーの皆さんにもお話を伺いました。
―team長崎・シークリーンに入ったきっかけを教えてください。
内野さん:
PTAのつながりで声をかけてもらったのがきっかけです。もともと自宅の前が漁港で、個人的にごみ拾いもしていたので、海のごみには関心がありました。
実際に活動に参加してみたら「これだな」と感じて、気づけばメンバーになっていて。

―ウニ養殖プロジェクトのご担当なんですね。
内野さん:
はい。私と息子、漁師の馬場さんが中心となって取り組んでいます。
―与える餌はどのように選んでいるのですか?
内野さん:
いろいろ試しましたが、ブロッコリーが一番おいしく育ちました。大根やにんじんも使いましたが、風味が少しウニに出るみたいで…。ウニって意外と何でも食べるんですよ。キャベツを使う研究もあるみたいです。


―どれくらいの頻度で餌を与えているんですか?
内野さん:
今は2週間に1回のペースで餌を与えています。
―第1クールではどのような気づきがありましたか?
内野さん:
最初はウニの扱いがよく分からなくて、うまく育ちませんでした。餌の量も1.8キロあげていたのですが、多かったようでかなり残ってしまったので、今は900グラムに減らしています。


―第2クールに向けた意気込みを教えてください!
内野さん:
ウニは気候や天候に敏感で、冬はあまり餌を食べなかったり、雨の日には弱ってしまうこともあるんです。そうした様子を見ながら餌やりの頻度を調整してきましたが、最近は気温も上がってウニの動きが活発になってきたので、次のクールでは餌の間隔を少し短くしたり、こまめに様子を見ながら育てていきたいと思っています。


大人も子どもも。地域と未来のために、できることから一歩ずつ。
―皆さん、「team長崎シー・クリーン」の立ち上げ当初から参加されているんですか?
メンバーの皆さん:
はい、そうです。
―参加されたきっかけは何だったのでしょうか?
向井さん:
私は野母崎に住んでいるのですが、軍艦島が見える場所の清掃活動をしていると聞いて。地元の住民として何かできればと思い、参加しました。

―今日のように、休日も使って活動されているんですね。どんな想いで続けているのでしょうか?
たけさん:
地元に住んでいるからこそ、この美しい海を守っていきたいという想いがあります。せっかく世界遺産の軍艦島が見える海なので、地元の人も観光客も気持ちよく訪れてもらえるように、きれいな状態で次の世代に残していきたいですね。
―環境の変化について、何か感じることはありますか?
向井さん:
先日、恐竜パーク周辺の清掃をしました。今回で5回目くらいになります。最初の頃はごみ袋4〜5袋分は出ていたのに、年々減ってきていると感じます。正直、増えているのかと思っていたので、ちょっと意外でした。

―今後取り組んでいきたいことはありますか?
向井さん:
私は地元で清掃業をしていることもあり、普段から環境のことには関心があります。今後はごみの問題だけでなく、他の環境関係のことも取り組んでいきたいですね。
学校やロータリークラブなどで、講演を行ったりしているのですが、今後も続けていきたいです。子どもたちにも関心を持ってもらえるよう、学校で話す機会があれば積極的に関わっていきたいです。
―子どもたちへの発信を大事にされているのですね。
たけさん:
小さいうちから触れることで、環境のことに興味を持つきっかけになってくれたらと思っています。学校や地域の中で「こういう活動があるんだ」と知ってもらうだけでも、考えるきっかけになると思います。今後も発信を続けていきたいです。
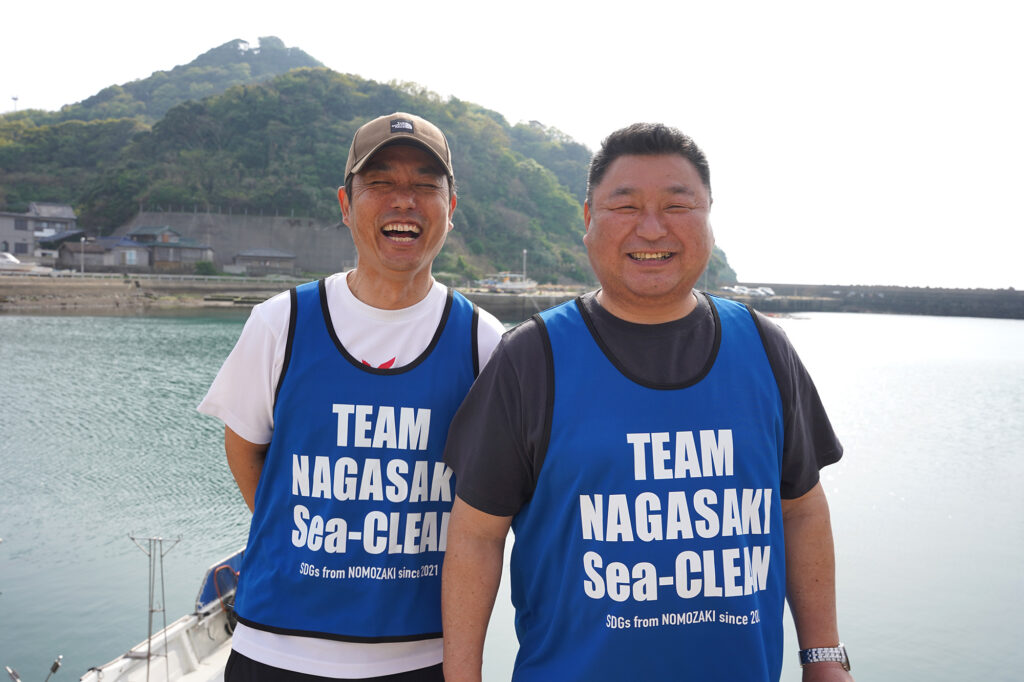
―学生メンバーにも話を伺いたいと思います。どんなことを考えながら、チーム活動をされているんでしょうか?
琉さん:
僕はまだ高校生なので、できることは限られています。でも、できる範囲で、何か行動したいと思っています。
中学生の頃、総合学習の時間に環境問題について発表する機会がありました。そのときに、ただ話すだけじゃ面白くないと思って、動画を作ったんです。仲間にインタビューして、ごみ拾いの様子を紹介する内容にしました。
―すごいですね。その動画の中で、どんなことを伝えたかったんですか?
琉さん:
自分たちが実際に活動している姿を見てもらうことで、少しでも関心を持ってもらえたらと思っていました。
小さいことでも自分たちにできることを一つずつ積み重ねていけば、きっと何かしらの結果につながるはず。だから、そうやって続けていくのが大切なんじゃないかなって思っています。

―普段から心がけていることはありますか?
琉さん:
車ではなく歩いたり、自転車に乗ったりしてます。それだけでもCO₂の削減につながるので、コツコツ続けていければと思っています。
また「ここに住みたか〜」と思える海に
―漁師を始めてどれくらいですか?
馬場さん:
40年くらいです。
―地球温暖化の影響はいつ頃から感じていますか?
馬場さん:
ここ10年くらいかな。
―どのような変化があるのでしょうか?
馬場さん:
海がね、よく「磯焼け」って言いますけど、あれは簡単に言えば“海が死んどる”状態。このあたりも、正直そう見えるとです。

―“死んだ海”というのは、どういう状態なんでしょう?
馬場さん:
海の透明度が、やたら良くなってきとるんです。一見きれいに見えるけど、実は植物プランクトンがおらん。そいが育たんことには、動物プランクトンや魚も育たんとですよ。
―以前はどうだったんですか?
馬場さん:
前は動物プランクトンもおったし、エイの子どもが泳ぎよるのも見よった。それが今は、さっぱり見らんごとなりました。
―季節によっても変化がありますか?
馬場さん:
12月から2月くらいの冬は特に海が澄んどります。暖かくなって、3月になると少し緑っぽくなってくる。今はその変化が薄かとです。
―それって見た目にも分かるものですか?
馬場さん:
よーく見たら、海の中にもやもや〜っとしたものが見えます。でも最近はそいが見えん。
―じゃあ今は、ずっと透き通ったまま?
馬場さん:
そうそう。透き通って、みんな「きれかね〜」って言うけど、本当は生き物が減っとるということ。“死んどる海”っちゅうことたいね。
―透き通っていたら良くないんですね。
馬場さん:
見た目はきれかけど、本当はよくない。この辺の水質は毎年ちゃんと調べてもらいよるんですが、報告する数字としては上等。でも実際はリンとか窒素とか、海にとって必要な栄養がぜんぜん足らん。海の中の生き物たちにとっちゃ、生きていけん環境になっとる。

―数値がいいというのは、人間側の基準ということですか?
馬場さん:
人間の目線では「上等な海水」やろうね。でも言ってみれば、酸素がなくて二酸化炭素ばっかりの部屋におるようなもん。
ホースを口にくわえて深呼吸してみてって言われたら、最初は吸えても、だんだん苦しゅうなるでしょう?海の中も同じ。海の中の生き物たちは息ができん状態になっとる。
―なるほど。それで海藻も育たなくなるんですね。
馬場さん:
そう。前はね、春になったら海藻が生え始めよった。4〜5月には、海藻を触ったらベロベロとした感触があって「ああ、今卵を出しよるとやな」って分かった。でも今は芽が出らんで、根を張る前に枯れてしまう。
―どうしてそうなってしまったのでしょう?
馬場さん:
たぶんね、この海の環境が「ここに住みたくなか」って、海藻に思わせてるんじゃなかかな。
それにせっかく芽が出ても、ウニがおったらすぐ食べられて育つ暇もなか。だからまずウニを減らして、海藻が育つチャンスを作らんといかんとです。

―ブロッコリーを餌にするウニ養殖は、何かのとっかかりになりそうですか?
馬場さん:
どうかな。まだまだ試行錯誤中だから。
養殖する前のウニはね、ほとんど実が入っとらんかった。身の色も黒ずんでて、とてもうまそうなウニには見えんかった。それがブロッコリーを餌にしたら、身の色が綺麗にオレンジになった。これは間違いなかですね。
―餌によって色も味も変わるんですね。
馬場さん:
そうそう。たとえば人参は色はよくなるけど水っぽかし、味がウニとは全然違う。大根だと白いウニになって、味はもう完全に大根の味(笑)。あれはアウトやったですね。

―うまくいけば、ある程度の規模で育てられる可能性も?
馬場さん:
もし順調にいけば、1つのカゴ10個〜20個で、居酒屋で出せるくらいはできると思う。
1カゴでウニを30個育てられたとして、20カゴで600個。昔で言えば、600個のウニで大体1キロ分の身が取れる。この辺の天然ウニは1キロ3万5000円〜4万円くらいで取引されるから、うまくいけばそれくらいの価値にはなるかもしれん。
―でも、そこまで育てるにはかなり手間がかかりそうですね。
馬場さん:
1キロ分のウニを作ろうとしたら、どれだけカゴが必要かって話ですよ。正直、まだまだ遠い道のりやと思います。
でも、それでも副収入ぐらいにしかならんです。
―ウニ漁の現状も大きく変わっているんですね。
馬場さん:
ここ2〜3年で、ウニ漁が商売にならんようになってきた。昔は樽いっぱいにウニを獲ったら、200グラムのカップが10個分取れることもあった。
でも段々ウニの身が減ってきて、カップ5個くらい分になって。5個でギリギリ商売になるくらいだったのに、今は同じ作業をしても、カップ1個か1個半くらいしか取れん。
ウニを割って、振って、身を取って、1日寝かして…作業は同じやけど、取れる量が5分の1、下手したらそれ以下。
夜中まで家族総出でやって、翌朝またすぐ海に出て…。それで商売にならないとなると「もうやめようか…」って気持ちになります。実際、やめた人も多かとですよ。


―ウニ以外の漁はどうですか?季節ごとに他の漁もされてるんですよね?
馬場さん:
はい。ウニの漁期はだいたい1カ月。アワビはもう少し長くて2カ月くらい。アワビが終わったら、今度は伊勢海老のシーズンになります。
―アワビや伊勢海老にも、やっぱり変化があるんですか?
馬場さん:
ありますよ。全部減っとる。量は減ったし、単価も落ちた。伊勢海老だけはなんとか値段を保っとるけど、それでもやっぱり前ほどは獲れん。
―それも温暖化の影響なのでしょうか?
馬場さん:
そう。温かい海のせいで、赤ハタとかキジハタとか「ハタ」系の魚が増えてきとるんです。ハタが伊勢海老の住処を奪ってしまってる。どちらも穴の中を好むんだけど、伊勢海老よりハタが大きいと、伊勢海老を追い出してしまう。
それで「稚エビ」が減ってる。結果的に、伊勢エビがどんどんおらんごとなってきとるんです。生態系がガラッと変わってきてる。
―10年くらい前から変化を感じ始めたんですよね。ここ10年の間でも変化はありましたか?
馬場さん:
10年ちょっと前は、ウニを駆除しただけで海藻が生え始めて、アワビも他の魚もたくさん取れるようになっていた。
高浜の漁師たちが中心になって藻場の再生に取り組んで、全国で発表して注目されたんですよ。水産大臣賞ももらって。
だけど、今はまた全然違う状況ですね。

―これから先、どんな想いで向き合っていきたいですか?
馬場さん:
これからどうなるか分からんけど、誰かひとりのせいじゃなかです。海自体が変わってきとる。そいが現実ですね。
やれることをコツコツやって、少しでも海の生き物が「ここに住みたか〜」って思わせる環境に戻していけたらと思っとります。


